

食中毒のうち40%が従業員による汚染というニュースを見たよ。
しっかり従業員教育をやっているはずなのに、どうして従業員が食品を汚染してしまうのだろう。
どのような食品営業施設でも、「正しい手洗いの方法」や「下痢・嘔吐があるときは出勤してはいけない」といった従業員教育は行っています。
しかし、従業員が原因の食中毒は依然として多く発生しています。
これにはさまざまな理由が考えられますが、その一つとして「教育を行ったからといって、従業員がその通り行動するとは限らない」があります。



みなさんも経験があるのではないでしょうか。
親や学校の先生から「勉強をやるように!」と言われて、それが正しい事だと分かっていても、ついつい遊んでしまう。
このように、「従来の知識を与える従業員教育だけでは食中毒を予防するのに不十分である」という認識が近年高まり、「食品安全文化」という形で、多くの国や民間の食品安全の基準に組み込まれ始めています。


食品安全文化では「行動科学」(Behavioral science)の考え方を取り入れ、従業員が適切な行動をとる組織文化の構築を目標にしています。このように、今後の食品安全には「行動科学」の考え方が重要なポイントです。
そこで、この記事では「行動科学」×「食品安全」の参考になる情報を紹介したいと思います。
今回紹介する記事は「Behavioral science and food safety」(行動科学と食品安全)です。(引用:Green LR. Behavioral science and food safety. J Environ Health. 2008 Sep;71(2):47-9. PMID: 18807824)



この記事は、飲食店の監視を行う保健所の職員向けに書かれたものです。しかし、食品事業者の方にとっても、従業員教育を行う上で参考になる内容だと思います。
食品の安全性は人間の行動に大きく作用される
外食産業で発生する食中毒のほとんどは、従業員の不適切な食品の取り扱いによるものです。つまり、人間の行動は飲食店が安全な食品を提供する上で最も重要な要素と言えます。
そのため、従業員の行動に変化をもたらす「行動科学」は、保健所の職員が食品営業施設を指導する際にも有用です。
保健所の職員は、食品営業施設に様々な情報を提供します。これは、情報(知識)を提供することで、従業員がその通り実践することを期待するからです。


しかし、知識は行動を変えるのに必要な要素かもしれませんが、それだけでは十分でありません。例えば、従業員教育を受けており正しい手順を知っていても、63%の従業員が常にそのとおりやっているわけではない、と回答しています。
ご存じの通り人間の行動は複雑であり、特定の行動をとるかどうかは、知識だけでなく様々な要因が影響します。例えば、時間の制約、十分な人員配置、適切なレイアウト・設備、上司や同僚の影響、個人の性格、作業手順などです。
そのため、保健所の職員は、従業員教育を提供する以上の、施設への介入が必要です。例えば、以下のような点についてマネージャーに助言を行うことです。
- マネージャーが食品安全の模範となる。
- マネージャーが食品安全の取組をサポートする。
- 安全な食品の取り扱いに影響を与える「要因」に対処する。(「要因」とは不十分な人員配置、不適切な設備など)
聞き取り調査に行動科学を取り入れる
保健所の職員は、飲食店に立ち入り検査をした際に、マネージャーや従業員に聞き取り調査を行います。
聞き取り調査の目的として、検査の時に見ただけでは分からない、普段の行動や食品の取り扱いを聞き出すためです。回答をもとに、食中毒が起きそうな施設かどうか判断するため、聞き取りは非常に重要です。
しかし、従業員からの回答が正確かどうかは疑問の余地があります。
聞き取り調査では通常、人は「良い人」に見られたいという動機が働きます。そのため、社会的に望ましい回答をしたり、聞き取る側が望んでいると思われる内容を回答しようとします。
聞き取り調査では、こうした動機によって正確な回答を得ることが困難です。特に、施設検査や食中毒調査のように、「間違った」回答をすることによって否定的な結果がもたらされる可能性がある場合に、この傾向は特に強くなります。
このような「不正確な回答」の影響は、完全に排除することはできません。しかし、行動科学の考え方を取り入れた聞き取り方法を用いることで、より正しい回答を得ることができます。
従業員を名前で呼ぶ、世間話をする、従業員の話に気を配るなどして、信頼関係を築く。これにより、従業員が安心し、調査に協力的になる。
中立性を保ち、「正しい」「間違っている」答えを従業員に伝えるような行動は控える。よくない例として、
- 意見を言う(例:「それはいい答えだ!」)
- 従業員が言っていることについて感情を「口頭」や「しぐさ」で伝える(例:顔をしかめる)
- 従業員が答えをためらっているときに、質問の答えを言う(例:「鶏肉は何度まで焼くのですか…74℃ですか?)
ある答えが他の答えより好ましいと思われるような質問は避ける。
例えば「肉を切った後、手を洗いましたよね?」


望ましい行動について尋ねる場合、その行動を前提とした質問は避ける。そのような前提は、「正しい」答えを示唆する可能性がある。
例えば、「食品安全トレーニングを受けた従業員は何人いますか」vs「食品安全トレーニングを受けている従業員はいますか」
好ましくない行動について質問するときは、正確な答えを得る確率を高めるため「誘導的な」質問をする。以下の2つの方法がある。
- 質問の中でその行動を想定する。
例えば、「あなたが手を洗えないとき、何がそれを妨げるのですか」(「もし洗えないとき」ではない) - 質問の中で、その行動が一般的であることを示す。
例えば、「どんなに優秀な従業員でも、食品の温度を毎回チェックできるわけではないです。あなたはどのくらいの頻度で食品の温度をチェックできないのですか」
特に答えにくい話題については、聞き取りの後半に質問する。これにより、従業員が保健所の職員と打ち解ける時間ができ、デリケートな質問が目立たなくなる。
質問の理由をきちんと説明する。目の前の問題を解決するためには、正確で正直な情報が重要であることを従業員に理解してもらうことで、役に立ちたいという気持ちに訴えかけることができる。
例えば、「鶏肉をどのように扱ったか教えてください。あなたの情報により、何が起こったかが理解でき、同じことが再び起こること防ぐことができます。」
可能であれば、秘密保持または匿名性を確保する。聞き取られる側(例:従業員)は、自分の発言が他人と共有されないとわかれば、正直に話しやすくなる。
保健所の職員が行動科学の考え方を取り入れることで、より正確な聞き取り調査を行えるようになります。これにより、飲食店で提供される食品の安全性がさらに向上することが期待されます。



以上が保健所の調査に行動科学の考え方を取り入れた例です。
どれも言われてみれば当たり前のような話ですが、意識して取り入れないと、なかなか実践できないことです。この記事が保健所の職員だけでなく、食品営業施設のマネージャーにも参考になればと思います。
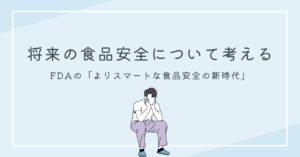
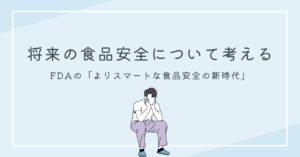
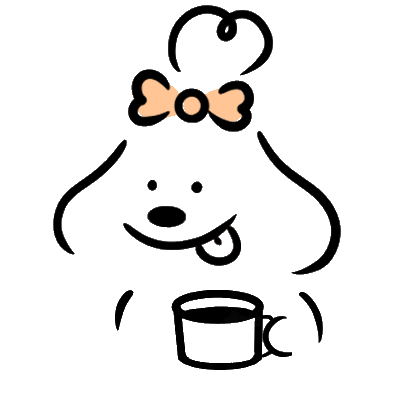
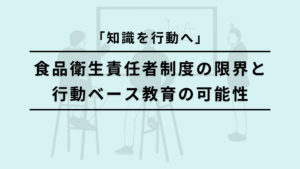
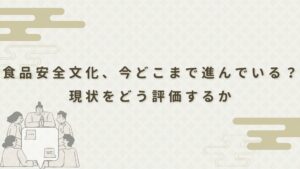

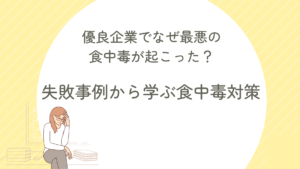
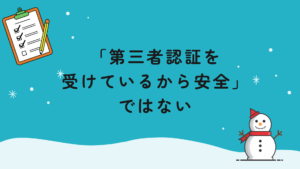
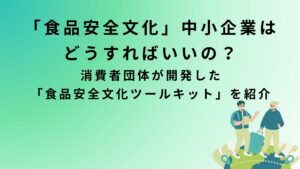
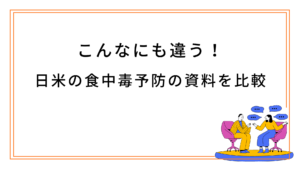
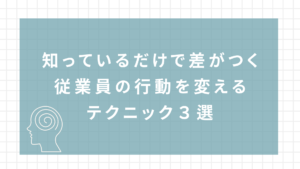
コメント